イトスギ
グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2014年08月26日
2014年08月25日
発掘情報館(渋川市)
先日、渋川市の「坂東梁」へ出掛けた帰り、すぐ近くなので「発掘情報館」へ立ち寄りました。

平成24年11月、渋川市にある「金井東裏遺跡」で発掘された「甲を着た古墳人」で注目されましたが、更に発掘調査は進められ、「首飾りの古墳人」等が見つかっているそうです。
情報館では夏休み中ということで「埴輪作り」の体験講座が開かれていて賑やかでした。
入口では可愛い埴輪のぐんまちゃんが出迎えてくれました。

個人的に、「埴輪ぐんまちゃん」のファンなので、つい写真を撮ってしまいました。
直ぐに「甲を着た古墳人」の展示があり、説明もとても丁寧です。

榛名山では古墳時代二度の大きな噴火があり、最初の噴火は6世紀初めで火山灰が降り、火砕流の堆積がみられます。二度目は6世紀半ばで、大量の軽石が降ったそうです。この「金井東裏遺跡」では両方の火山噴出物が堆積していて、上の写真の白い部分が軽石(厚さ2m)で、黒い部分が火山灰と火砕流の堆積物だそうで、甲の人は黒い部分の最初の噴火の噴出物の下からうつ伏せ状態で発掘されたそうです。
身に着けていた甲は「小札甲(こざねよろい)」と呼ばれるもので、小さな鉄板を800〜1000枚程を繋ぎ合わせて作られた物だそうです。更に詳細調査し内部に詰まっていた火砕流を取り除いたところ、骨製の小札が繋がった状態で見つかり、これは日本国内で初めての発見ということで話題になった様です。
恥ずかしいのですが、「甲を着た古墳人」発掘のことは知っていて、甲の形状がきれいに残っているな・・・位の知識しかありませんでしたので、骨製の小札を身につけていたことに驚きました。その様な細かい細工が可能だとは信じられない思いです。
進んだ技巧といえば、

ここに示されているような「渡り腮仕口(わたりあごしくち)」、「通し枘(ほぞ)」、「包込枘」、「相欠き仕口」等、今日の木材加工の手法に用いられているものが縄文時代のこの富山県小矢部市の「桜町遺跡」の高床建物から発見されているそうです。
特に「渡り腮仕口」は法隆寺に最古の使用例が認められているというもので、その技工のの素晴らしさは想像を絶します。
丁寧に見学しているととても見ごたえがあり、何度か訪れたい所です。
館内にはこんな立派な収蔵庫もあり、公開されています。

展示の多さ、説明の丁寧さ、展示の工夫等、とても魅力的です。
中にこんな埴輪がありました。

誰でしょう?

平成24年11月、渋川市にある「金井東裏遺跡」で発掘された「甲を着た古墳人」で注目されましたが、更に発掘調査は進められ、「首飾りの古墳人」等が見つかっているそうです。
情報館では夏休み中ということで「埴輪作り」の体験講座が開かれていて賑やかでした。
入口では可愛い埴輪のぐんまちゃんが出迎えてくれました。

個人的に、「埴輪ぐんまちゃん」のファンなので、つい写真を撮ってしまいました。
直ぐに「甲を着た古墳人」の展示があり、説明もとても丁寧です。

榛名山では古墳時代二度の大きな噴火があり、最初の噴火は6世紀初めで火山灰が降り、火砕流の堆積がみられます。二度目は6世紀半ばで、大量の軽石が降ったそうです。この「金井東裏遺跡」では両方の火山噴出物が堆積していて、上の写真の白い部分が軽石(厚さ2m)で、黒い部分が火山灰と火砕流の堆積物だそうで、甲の人は黒い部分の最初の噴火の噴出物の下からうつ伏せ状態で発掘されたそうです。
身に着けていた甲は「小札甲(こざねよろい)」と呼ばれるもので、小さな鉄板を800〜1000枚程を繋ぎ合わせて作られた物だそうです。更に詳細調査し内部に詰まっていた火砕流を取り除いたところ、骨製の小札が繋がった状態で見つかり、これは日本国内で初めての発見ということで話題になった様です。
恥ずかしいのですが、「甲を着た古墳人」発掘のことは知っていて、甲の形状がきれいに残っているな・・・位の知識しかありませんでしたので、骨製の小札を身につけていたことに驚きました。その様な細かい細工が可能だとは信じられない思いです。
進んだ技巧といえば、

ここに示されているような「渡り腮仕口(わたりあごしくち)」、「通し枘(ほぞ)」、「包込枘」、「相欠き仕口」等、今日の木材加工の手法に用いられているものが縄文時代のこの富山県小矢部市の「桜町遺跡」の高床建物から発見されているそうです。
特に「渡り腮仕口」は法隆寺に最古の使用例が認められているというもので、その技工のの素晴らしさは想像を絶します。
丁寧に見学しているととても見ごたえがあり、何度か訪れたい所です。
館内にはこんな立派な収蔵庫もあり、公開されています。

展示の多さ、説明の丁寧さ、展示の工夫等、とても魅力的です。
中にこんな埴輪がありました。

誰でしょう?
2014年08月22日
国宝・臼杵石仏
九州旅行の最後の目的地、大分県臼杵市大字中尾・深田にある国宝臼杵石仏を訪れました。
石仏は「ホキ石仏第一群(堂ヶ迫石仏群)」・「ホキ石仏第二群」・「古園石仏群」・「山王石仏群」の四群、60余躯の磨崖仏で、1995年、磨崖仏としては日本で初めて国宝に指定されました。(指定対象は59躯)
造営の時期等を記す史料は一切残っていないため正確なことは解っていませんが、作風から、平安末期から鎌倉にかけて製作されたと考えられています。
先ず「ホキ第二群」から廻りました。

これはその内の「第一龕」です。(他に第二龕)
精神性が伺える表情、姿の美しさ等、千年を経ても尚心に響いてくるものを感じます。
静謐さの中に不思議な温かさが感じられることも臼杵石仏の特徴かもしれません。
阿蘇山からの火砕流が溶結した凝灰岩に彫られた石仏は脆く、劣化による柔らかみが加わっていることも大きいのではないかと思われます。
多くの石仏の下半身が無くなっているのもこの脆さのためで、現在ではこの様な建家に収められ、様々な工夫により劣化が抑えられているそうです。

次は「ホキ第一群」です。(全四龕)

ここの石仏には色彩が残されていることが肉眼でもよく解ります。

嘗ての華やかさを思うと圧倒される思いです。

これは「三王山石仏」の丈六の如来像ですが、何とも可愛らしく、童の様なお顔です。

かなり歩いていて疲れているにも拘らず、疲れも忘れてお顔に見惚れてしまいいました。
最後は最も有名で、臼杵の代表の様な「古園石仏群」です。

金剛界大日如来坐像を中心に、如来像2躯、菩薩像2躯、明王像2躯、天部像1躯、の全13躯から成、大日如来像の頭部は1994年、保存修復が完了するまで仏体下の台座に置かれたままでした。何とも異様な風景ですが、当時、仏頭を元に戻すかどうか激しい論争があったそうですが、仏頭の元の位置への修復が国保指定の条件となったため、最終的に現在の様に復元されました。
九州の石の文化に多く触れ、その素晴らしさに圧倒される旅でした。最後に、石仏群のある高台から下を見ると、極楽浄土の様な蓮池に蓮の花が満開で、多くの人々がそぞろ歩いている様子に、「ここは本当に極楽かも・・・」という錯覚を覚えるほど心穏やかな気分でした。

臼杵の駅へ向かい、電車を待っていると、これからが祇園祭りの本番というのに激しい雷が鳴り始め、その音に見送られながら帰路につきました。
石仏は「ホキ石仏第一群(堂ヶ迫石仏群)」・「ホキ石仏第二群」・「古園石仏群」・「山王石仏群」の四群、60余躯の磨崖仏で、1995年、磨崖仏としては日本で初めて国宝に指定されました。(指定対象は59躯)
造営の時期等を記す史料は一切残っていないため正確なことは解っていませんが、作風から、平安末期から鎌倉にかけて製作されたと考えられています。
先ず「ホキ第二群」から廻りました。

これはその内の「第一龕」です。(他に第二龕)
精神性が伺える表情、姿の美しさ等、千年を経ても尚心に響いてくるものを感じます。
静謐さの中に不思議な温かさが感じられることも臼杵石仏の特徴かもしれません。
阿蘇山からの火砕流が溶結した凝灰岩に彫られた石仏は脆く、劣化による柔らかみが加わっていることも大きいのではないかと思われます。
多くの石仏の下半身が無くなっているのもこの脆さのためで、現在ではこの様な建家に収められ、様々な工夫により劣化が抑えられているそうです。

次は「ホキ第一群」です。(全四龕)

ここの石仏には色彩が残されていることが肉眼でもよく解ります。

嘗ての華やかさを思うと圧倒される思いです。

これは「三王山石仏」の丈六の如来像ですが、何とも可愛らしく、童の様なお顔です。

かなり歩いていて疲れているにも拘らず、疲れも忘れてお顔に見惚れてしまいいました。
最後は最も有名で、臼杵の代表の様な「古園石仏群」です。

金剛界大日如来坐像を中心に、如来像2躯、菩薩像2躯、明王像2躯、天部像1躯、の全13躯から成、大日如来像の頭部は1994年、保存修復が完了するまで仏体下の台座に置かれたままでした。何とも異様な風景ですが、当時、仏頭を元に戻すかどうか激しい論争があったそうですが、仏頭の元の位置への修復が国保指定の条件となったため、最終的に現在の様に復元されました。
九州の石の文化に多く触れ、その素晴らしさに圧倒される旅でした。最後に、石仏群のある高台から下を見ると、極楽浄土の様な蓮池に蓮の花が満開で、多くの人々がそぞろ歩いている様子に、「ここは本当に極楽かも・・・」という錯覚を覚えるほど心穏やかな気分でした。

臼杵の駅へ向かい、電車を待っていると、これからが祇園祭りの本番というのに激しい雷が鳴り始め、その音に見送られながら帰路につきました。
2014年08月20日
「臼杵(うすき)」の早朝散策
何時も通り早朝に起きてしまったので、臼杵の町をぶらぶら歩いてみることにしました。
臼杵は戦国時代、大友宗麟により築かれた「臼杵城」を中心にした城下町で、町並みに歴史を感じさせる所が多いです。

この看板はお醤油屋さんのもので、あまりの難しい漢字に思わず写真を撮ってしまいましたが、何と読むのか分からなくなってしまいました。

町中には至る所にお寺があります。
こちらは「旧真光寺」で、町並み散策の無料休憩所となっているそうですが、早朝なので締まっていました。

ここから立派な三重塔が見えたので近づいてみると、

「龍原寺三重塔」で、太子塔とも呼ばれる聖徳太子を祀る塔でした。
安政5年(1858)竣工のこの塔は九州に2つしかない江戸期の木造三重塔の一つだそうで、なかなかに見事です。
臼杵は高低差の多い趣のある町で、細い路地を抜けると石段のの上にお寺が見えたりして楽しいです。

ここは「清光山月光寺」です。
静かな町並みを散策していると、何やら法被にハチマキ姿の人が見られるようになりましたが、今日が「臼杵祇園祭り」なのだそうです。
今回の旅はお祭りに始まりお祭りに終わりました。
折角なので「臼杵城跡」も散策してみました。

大友宗麟が臼杵湾に浮かぶ丹生島に築いた海城で、島の形が亀に似ていたことから別名「亀城(きじょう)とも呼ばれ、断崖絶壁で四方を囲まれた城だったそうですが、現在は埋め立てにより陸続きなっています。
嘗ては数多くの櫓が立ち並んでいましたが、現在は畳櫓、卯寅口(うとのくち)門脇櫓等の近世の遺構が残されている他、「大門櫓」が復元されています。本丸と二の丸の間には空堀が現存、比較的遺構を留めていますが周辺は総て埋め立てられているため嘗ての海城の面影は失われています。県の史跡に指定されています。
お城からの眺めはこんな感じです。

卯寅口櫓の横には鮮やかな「卯寅稲荷」がありました。

臼杵の町並散策を終え、これから「臼杵石仏」見学に向かいます。
臼杵は戦国時代、大友宗麟により築かれた「臼杵城」を中心にした城下町で、町並みに歴史を感じさせる所が多いです。

この看板はお醤油屋さんのもので、あまりの難しい漢字に思わず写真を撮ってしまいましたが、何と読むのか分からなくなってしまいました。

町中には至る所にお寺があります。
こちらは「旧真光寺」で、町並み散策の無料休憩所となっているそうですが、早朝なので締まっていました。

ここから立派な三重塔が見えたので近づいてみると、

「龍原寺三重塔」で、太子塔とも呼ばれる聖徳太子を祀る塔でした。
安政5年(1858)竣工のこの塔は九州に2つしかない江戸期の木造三重塔の一つだそうで、なかなかに見事です。
臼杵は高低差の多い趣のある町で、細い路地を抜けると石段のの上にお寺が見えたりして楽しいです。

ここは「清光山月光寺」です。
静かな町並みを散策していると、何やら法被にハチマキ姿の人が見られるようになりましたが、今日が「臼杵祇園祭り」なのだそうです。
今回の旅はお祭りに始まりお祭りに終わりました。
折角なので「臼杵城跡」も散策してみました。

大友宗麟が臼杵湾に浮かぶ丹生島に築いた海城で、島の形が亀に似ていたことから別名「亀城(きじょう)とも呼ばれ、断崖絶壁で四方を囲まれた城だったそうですが、現在は埋め立てにより陸続きなっています。
嘗ては数多くの櫓が立ち並んでいましたが、現在は畳櫓、卯寅口(うとのくち)門脇櫓等の近世の遺構が残されている他、「大門櫓」が復元されています。本丸と二の丸の間には空堀が現存、比較的遺構を留めていますが周辺は総て埋め立てられているため嘗ての海城の面影は失われています。県の史跡に指定されています。
お城からの眺めはこんな感じです。

卯寅口櫓の横には鮮やかな「卯寅稲荷」がありました。

臼杵の町並散策を終え、これから「臼杵石仏」見学に向かいます。
2014年08月17日
豆腐と餃子の皮で簡単ラザニア
先日、15才の中学生が遊びに来たので、簡単で楽しいレシピにしてみました。
これは7月に九州の親戚宅でご馳走になり、簡単で美味しかったので、中学生にレシピを教えてあげようと作ってみました。

作り方はごく簡単で、お豆腐は水切りしてカッターでペースト状にし、ミートソースを用意(市販のもので良いのですが、私は鶏ミンチで手造りしました。中学生のダイエット志向にも配慮して、鶏肉にし、味付けも和風にしました)。餃子の皮は10〜12枚、後はパルミジャーノ・レッジャーノチーズを用意するだけです。
耐熱の器に、豆腐・ミートソース・餃子の皮・チーズ(卸して)の順に重ねてゆき、最後はチーズにして、180位のオーブンで25分位焼けば出来上がりです。
お豆腐には軽く塩味をつけても良いですが、美味しいお豆腐だったら何もいりません。
とても好評でした。
他には簡単な「ホットプレートパエリア」と庭で収穫したトマトとナスがメインの昆布味の「ラタトゥイユ」でした。

簡単な上に喜んでもらえて嬉しかったです。
こんなレシピもたまには楽しいものだと思いました。
これは7月に九州の親戚宅でご馳走になり、簡単で美味しかったので、中学生にレシピを教えてあげようと作ってみました。

作り方はごく簡単で、お豆腐は水切りしてカッターでペースト状にし、ミートソースを用意(市販のもので良いのですが、私は鶏ミンチで手造りしました。中学生のダイエット志向にも配慮して、鶏肉にし、味付けも和風にしました)。餃子の皮は10〜12枚、後はパルミジャーノ・レッジャーノチーズを用意するだけです。
耐熱の器に、豆腐・ミートソース・餃子の皮・チーズ(卸して)の順に重ねてゆき、最後はチーズにして、180位のオーブンで25分位焼けば出来上がりです。
お豆腐には軽く塩味をつけても良いですが、美味しいお豆腐だったら何もいりません。
とても好評でした。
他には簡単な「ホットプレートパエリア」と庭で収穫したトマトとナスがメインの昆布味の「ラタトゥイユ」でした。

簡単な上に喜んでもらえて嬉しかったです。
こんなレシピもたまには楽しいものだと思いました。
2014年08月14日
「熊野磨崖仏」と「両子寺(ふたごじ)」
富貴寺の次に向かったのは、九体の重要文化財の仏像を有する、
豊後高田市田染(たしぶ)真木にある「真木大堂」ですが、平成20年の収蔵庫改修により、立派な建物に安置されていて撮影は出来ず、建物も収蔵庫のみ・・・ということで、写真がありません。
真木大堂は六郷満山の本山本寺(もとやまほんじ)であった「馬城山伝乗寺(まきさんでんじょうじ)」の堂宇の一つであったと伝えられ、往時は広大な境内に七堂伽藍を備えて隆盛を誇った「幻の寺院」とされてきましたが、約700年前焼失。現存する九体の仏像が修復され現在に至っています。平安期の作とみられる仏像は素晴らしいです。
裏手にはこの地域に散在していた石塔・石仏を一同に集めた古代文化公園が整備されているそうです。
次に向かたのは「熊野磨崖仏」です。

豊後高田市田染の田原山(鋸山)山麓の今熊野山胎蔵寺(いまくまのさんたいぞうじ)の脇から急な坂道を300m程登ると、鬼が一夜にして積み上げたという伝説の残る、自然石を乱積にした石段があり、この石段を登った所の岸壁に二体の巨大な磨崖仏が現れます。
向かって左が高さ8メートルの半立像の、何とも親しみやすい表情の「不動明王像」です。両眼が突出しているのが特徴です。
比較的加工しやい岸壁に刻まれているため風化が進行していることにもよるのでしょうが、柔和な表情が明王像とは思えない雰囲気を漂わせています。

右手は高さ6.7mの半身像の「大日如来像」で、高さ8mの龕・がん(くぼみ)の中に彫り出されています。
知的な表情の中に優しさが感じられます。

二体の磨崖仏の奥に熊野神社があるそうですが、暑さにめげ、パスしました。
でも汗をかいてキツイ山道を登った甲斐は大いにあり、爽やかな気分でした。
次に訪れたのは「両子寺」です。
国東半島のほぼ真ん中に位置し、修行の中心地として栄え、江戸時代には六郷満山の総持寺として満山を統括していました。
山門に続く石段の両脇には江戸時代後期の作とされる国東半島最大級とされる、総高245mの石像の仁王像が立ち、絶好の撮影ポイントとされているそうで、秋の紅葉の時期は混雑するそうです。

確かに、人を入れずに写真を撮るのは難しかったです。
この寺は子授けの寺としても有名だそうです。
階段を上がった所に護摩堂があり、更に上ると奥の院があるそうでしたが、奥の院はパスしました。

そろそろ体力も限界なので、終点の大分駅まで大人しく乗ってゆくことにしました。
大分駅からは、臼杵まで移動。
明日は臼杵の石仏に会いに行きます。
豊後高田市田染(たしぶ)真木にある「真木大堂」ですが、平成20年の収蔵庫改修により、立派な建物に安置されていて撮影は出来ず、建物も収蔵庫のみ・・・ということで、写真がありません。
真木大堂は六郷満山の本山本寺(もとやまほんじ)であった「馬城山伝乗寺(まきさんでんじょうじ)」の堂宇の一つであったと伝えられ、往時は広大な境内に七堂伽藍を備えて隆盛を誇った「幻の寺院」とされてきましたが、約700年前焼失。現存する九体の仏像が修復され現在に至っています。平安期の作とみられる仏像は素晴らしいです。
裏手にはこの地域に散在していた石塔・石仏を一同に集めた古代文化公園が整備されているそうです。
次に向かたのは「熊野磨崖仏」です。

豊後高田市田染の田原山(鋸山)山麓の今熊野山胎蔵寺(いまくまのさんたいぞうじ)の脇から急な坂道を300m程登ると、鬼が一夜にして積み上げたという伝説の残る、自然石を乱積にした石段があり、この石段を登った所の岸壁に二体の巨大な磨崖仏が現れます。
向かって左が高さ8メートルの半立像の、何とも親しみやすい表情の「不動明王像」です。両眼が突出しているのが特徴です。
比較的加工しやい岸壁に刻まれているため風化が進行していることにもよるのでしょうが、柔和な表情が明王像とは思えない雰囲気を漂わせています。

右手は高さ6.7mの半身像の「大日如来像」で、高さ8mの龕・がん(くぼみ)の中に彫り出されています。
知的な表情の中に優しさが感じられます。

二体の磨崖仏の奥に熊野神社があるそうですが、暑さにめげ、パスしました。
でも汗をかいてキツイ山道を登った甲斐は大いにあり、爽やかな気分でした。
次に訪れたのは「両子寺」です。
国東半島のほぼ真ん中に位置し、修行の中心地として栄え、江戸時代には六郷満山の総持寺として満山を統括していました。
山門に続く石段の両脇には江戸時代後期の作とされる国東半島最大級とされる、総高245mの石像の仁王像が立ち、絶好の撮影ポイントとされているそうで、秋の紅葉の時期は混雑するそうです。

確かに、人を入れずに写真を撮るのは難しかったです。
この寺は子授けの寺としても有名だそうです。
階段を上がった所に護摩堂があり、更に上ると奥の院があるそうでしたが、奥の院はパスしました。

そろそろ体力も限界なので、終点の大分駅まで大人しく乗ってゆくことにしました。
大分駅からは、臼杵まで移動。
明日は臼杵の石仏に会いに行きます。
2014年08月14日
渋川・坂東梁
来客があり、渋川の「坂東梁」へ鮎料理を食べに出掛けました。
以前「磯部梁」へ何度か出掛けたのですが、梁はすっかり飾り物になっていて侘しかったので、現役の梁へ行ってみたくて探しました。

現在は、残念ながら水量が少なく、梁に踊る鮎は見られませんでしたが、増水時、上流を塞き止めると梁として充分機能するようです。
梁の造りも全く違います。

梁の下には川の水で梁が浮き上がらない様に川石を沢山詰めた重しが所々に設置され、「生きている梁」といった感じです。(分かり難いですが、写真中央の梁の下に見えます)

座敷へあがる入口には「焼き場」があり、猛烈な熱気が立ち込めていました。

大きな扇風機は回っているものの、殆ど熱風で、焼き場の方々は滴る汗の中での過酷な仕事です。
特にこの日群馬では37〜38度という猛暑でしたので、室内は凄まじい暑さでした。
唐揚げは直ぐに出てくるのですが、塩焼きは30分以上かかります。
その間、お庭を散策してみました。
川の水を引いた生簀には元気な鮎がいっぱいです。

庭には今「珊瑚樹」の実が沢山ついていました。

漸く焼きあがった鮎がきたのですが、あっという間に食べてしまい、写真がありません!
帰り、焼き場の方とお話していたら、骨せんべいを試食させていただき、美味しかったのでお土産に頂いてきました。
漸く本来の梁で鮎料理が食べられ、満足です。
以前「磯部梁」へ何度か出掛けたのですが、梁はすっかり飾り物になっていて侘しかったので、現役の梁へ行ってみたくて探しました。

現在は、残念ながら水量が少なく、梁に踊る鮎は見られませんでしたが、増水時、上流を塞き止めると梁として充分機能するようです。
梁の造りも全く違います。

梁の下には川の水で梁が浮き上がらない様に川石を沢山詰めた重しが所々に設置され、「生きている梁」といった感じです。(分かり難いですが、写真中央の梁の下に見えます)

座敷へあがる入口には「焼き場」があり、猛烈な熱気が立ち込めていました。

大きな扇風機は回っているものの、殆ど熱風で、焼き場の方々は滴る汗の中での過酷な仕事です。
特にこの日群馬では37〜38度という猛暑でしたので、室内は凄まじい暑さでした。
唐揚げは直ぐに出てくるのですが、塩焼きは30分以上かかります。
その間、お庭を散策してみました。
川の水を引いた生簀には元気な鮎がいっぱいです。

庭には今「珊瑚樹」の実が沢山ついていました。

漸く焼きあがった鮎がきたのですが、あっという間に食べてしまい、写真がありません!
帰り、焼き場の方とお話していたら、骨せんべいを試食させていただき、美味しかったのでお土産に頂いてきました。
漸く本来の梁で鮎料理が食べられ、満足です。
2014年08月08日
宇佐神宮
福江空港からゆるキャラの「バラモン君」に見送られ、

再び博多空港へ向かいましたが、今回は天気も良く、窓からは蒼い海に浮かぶ大小の島々が見られ、少し大きな島には人の営みが窺える建物や漁港等が遠目に見られました。

博多から大分へ出て宇佐へ向かいました。
翌日国東半島を巡る予定でしたので、この日は宇佐神宮真ん前の宿に泊まり、翌朝宇佐神宮を散策する予定です。
翌朝は早くに目覚めてしまったので、5時半頃、早朝の神宮散策に出掛けました。
参道を抜けると何やら不思議な物が見えました。

「26号蒸気機関車・クラウス号」で明治24年ドイツ製で県指定有形文化財です。
昭和23年、国鉄から大分交通に譲られ、宇佐駅と宇佐神宮を結ぶ鉄道の主役として昭和40年まで活躍したそうです。
突然の蒸気機関車にびっくり?です。
宇佐神宮は全国八幡宮の総本宮で、神輿と神仏習合の発祥地として有名です。
神橋を渡り大鳥居を潜ると

右手に初澤池があり、「原始蓮」がきれいに咲いていましたが、何やら音が聞こえています。
気づくと蓮の開花の音でした。

話には聞いていましたが、実際に耳にするのは初めてです。
ここから爽やか空気の中を「上宮」に向かって進みました。
途中の池の辺では鴨がお休み中でしたが、近づいても全く逃げないので横をそっと通り抜けました。

なんとも長閑な雰囲気の中を散策、上宮入口の「西大門」へ出ました。

桃山文化の華麗な唐破風の門です。
本殿は改修中でしたが、県指定有形文化財の見事な「南中楼門」(勅使門)が厳かに佇み

その横には宇佐神宮御祭神の三柱の一之御殿「八幡大神」(応神天皇)、二之御殿「比売大神」(多岐津姫命)三之御殿「神功皇后」(息長帯姫命)が並んでいました。

ここから下って下宮(御炊殿といい、神へ捧げる食事を用意する所)へ向かい、神仏習合発祥の地の「弥勒寺跡」へ行ってみましたが、虫が酷く近づけませんでした。

738年に建立され国東半島の六郷満山文化に大きな影響を与え、明治時代廃寺となりましたがかなり立派なお寺だった様です。
更に下ると、嘗ては弥勒寺の仁王門ヘと続く橋だった県有形文化財の「呉橋」が見えてきました。

境内の社殿同様、檜皮葺きの唐破風の屋根に覆われた立派な橋で、10年に一度の勅使祭の時だけ扉が開けられるそうです。
早朝の散策は涼しい上に虫の被害も少なく大正解でした。
この後、観光バスで国東半島を巡ることにしました。

再び博多空港へ向かいましたが、今回は天気も良く、窓からは蒼い海に浮かぶ大小の島々が見られ、少し大きな島には人の営みが窺える建物や漁港等が遠目に見られました。

博多から大分へ出て宇佐へ向かいました。
翌日国東半島を巡る予定でしたので、この日は宇佐神宮真ん前の宿に泊まり、翌朝宇佐神宮を散策する予定です。
翌朝は早くに目覚めてしまったので、5時半頃、早朝の神宮散策に出掛けました。
参道を抜けると何やら不思議な物が見えました。

「26号蒸気機関車・クラウス号」で明治24年ドイツ製で県指定有形文化財です。
昭和23年、国鉄から大分交通に譲られ、宇佐駅と宇佐神宮を結ぶ鉄道の主役として昭和40年まで活躍したそうです。
突然の蒸気機関車にびっくり?です。
宇佐神宮は全国八幡宮の総本宮で、神輿と神仏習合の発祥地として有名です。
神橋を渡り大鳥居を潜ると

右手に初澤池があり、「原始蓮」がきれいに咲いていましたが、何やら音が聞こえています。
気づくと蓮の開花の音でした。

話には聞いていましたが、実際に耳にするのは初めてです。
ここから爽やか空気の中を「上宮」に向かって進みました。
途中の池の辺では鴨がお休み中でしたが、近づいても全く逃げないので横をそっと通り抜けました。

なんとも長閑な雰囲気の中を散策、上宮入口の「西大門」へ出ました。

桃山文化の華麗な唐破風の門です。
本殿は改修中でしたが、県指定有形文化財の見事な「南中楼門」(勅使門)が厳かに佇み

その横には宇佐神宮御祭神の三柱の一之御殿「八幡大神」(応神天皇)、二之御殿「比売大神」(多岐津姫命)三之御殿「神功皇后」(息長帯姫命)が並んでいました。

ここから下って下宮(御炊殿といい、神へ捧げる食事を用意する所)へ向かい、神仏習合発祥の地の「弥勒寺跡」へ行ってみましたが、虫が酷く近づけませんでした。

738年に建立され国東半島の六郷満山文化に大きな影響を与え、明治時代廃寺となりましたがかなり立派なお寺だった様です。
更に下ると、嘗ては弥勒寺の仁王門ヘと続く橋だった県有形文化財の「呉橋」が見えてきました。

境内の社殿同様、檜皮葺きの唐破風の屋根に覆われた立派な橋で、10年に一度の勅使祭の時だけ扉が開けられるそうです。
早朝の散策は涼しい上に虫の被害も少なく大正解でした。
この後、観光バスで国東半島を巡ることにしました。
2014年08月04日
武家屋敷通りと五島観光歴史資料館
午後は晴れ間も出て、かなり蒸し暑くなりましたが、バスで通った武家屋敷通りで見かけた、家の周りを囲う石垣に興味を持ち、実物を見てみたくなり、出掛けました。

「こぼれ石」という丸い石が積み上げられ、今にも崩れそう!
最近のものはしっかりコンクリートで固められていましたが、昔ながらのものはゴロゴロと石が積まれているだけで、両端は半月型の石で止められています。なんともユニークで楽しい造りです。
武家屋敷通りにはふるさと館があり、こんな珍しい樹がありました。


展示室には五島でよく耳にする「バラモン」凧が販売されていました。

「バラモン」とは「ばらか」に由来し、「荒々しく向こう見ず」「活発で元気がよい」という意味だそうで、男の子の出産時等に贈られるそうです。
もう一つ不思議な響きの言葉がありました。「チャンココ」です。

こんな衣装で踊るお盆の行事だそうです。「チャン」が鉦(かね)の音、「ココ」は太鼓を叩く音であろうと言われています。
チャンココは各町内の青年団で構成され、伝統芸能として県指定無形文化財となっているそうです。

武家屋敷通り近くに「五島観光歴史資料館」があり、涼しい館内に魅力もあり入ってみました。
展示は農具、民俗行事、捕鯨の歴史、遣唐使と倭寇、五島藩の歴史、キリシタン文化、等々きめ細かく丁寧で見ごたえがありました。
入館者が少なかったので、学芸員の方に声をかけられ、「群馬県から来ました」と答えると、「ああ、あの富岡製糸工場ですね」と直ぐに反応が帰ってくるのは世界遺産になったおかげなのでしょう。意外にもここ五島からも富岡製糸工場へ工女として一年働いた女性がいたそうです。
船を乗り継いでの旅、さぞ苦難であったことか・・・と思います。「五島人は辛抱強い」といわれるそうですが、過酷な自然環境の中で育つと自然とそのように育つものなのかもしれません。
学芸員の方が、五島の城が海城といわれる証拠が見られます・・・と案内してくださったのが、

ここに船が着き、直接城へ入れたそうです。
福江城は、石田城ともいわれ、文久3年(1863)築の江戸時代最後の城郭で、黒船来航に備えて造られたため目立つ天守閣は無く、本丸の館も平屋だったが、明治維新を迎え築城9年後には解体されるという悲運を体験していますが、裏門にあたる蹴出門と城壁が修復を重ねながら現存しています。

又本丸跡には五島高等学校があります。
短い時間でしたが、五島列島をのんびり楽しめました。
欲張り旅になってしまったので、これから博多へ戻り、大分方面へ向かいます。

「こぼれ石」という丸い石が積み上げられ、今にも崩れそう!
最近のものはしっかりコンクリートで固められていましたが、昔ながらのものはゴロゴロと石が積まれているだけで、両端は半月型の石で止められています。なんともユニークで楽しい造りです。
武家屋敷通りにはふるさと館があり、こんな珍しい樹がありました。


展示室には五島でよく耳にする「バラモン」凧が販売されていました。

「バラモン」とは「ばらか」に由来し、「荒々しく向こう見ず」「活発で元気がよい」という意味だそうで、男の子の出産時等に贈られるそうです。
もう一つ不思議な響きの言葉がありました。「チャンココ」です。

こんな衣装で踊るお盆の行事だそうです。「チャン」が鉦(かね)の音、「ココ」は太鼓を叩く音であろうと言われています。
チャンココは各町内の青年団で構成され、伝統芸能として県指定無形文化財となっているそうです。

武家屋敷通り近くに「五島観光歴史資料館」があり、涼しい館内に魅力もあり入ってみました。
展示は農具、民俗行事、捕鯨の歴史、遣唐使と倭寇、五島藩の歴史、キリシタン文化、等々きめ細かく丁寧で見ごたえがありました。
入館者が少なかったので、学芸員の方に声をかけられ、「群馬県から来ました」と答えると、「ああ、あの富岡製糸工場ですね」と直ぐに反応が帰ってくるのは世界遺産になったおかげなのでしょう。意外にもここ五島からも富岡製糸工場へ工女として一年働いた女性がいたそうです。
船を乗り継いでの旅、さぞ苦難であったことか・・・と思います。「五島人は辛抱強い」といわれるそうですが、過酷な自然環境の中で育つと自然とそのように育つものなのかもしれません。
学芸員の方が、五島の城が海城といわれる証拠が見られます・・・と案内してくださったのが、

ここに船が着き、直接城へ入れたそうです。
福江城は、石田城ともいわれ、文久3年(1863)築の江戸時代最後の城郭で、黒船来航に備えて造られたため目立つ天守閣は無く、本丸の館も平屋だったが、明治維新を迎え築城9年後には解体されるという悲運を体験していますが、裏門にあたる蹴出門と城壁が修復を重ねながら現存しています。

又本丸跡には五島高等学校があります。
短い時間でしたが、五島列島をのんびり楽しめました。
欲張り旅になってしまったので、これから博多へ戻り、大分方面へ向かいます。
2014年08月02日
五島列島
宗像大社、宮地嶽神社を巡った後は、博多から新幹線でひと駅の博多南にある親戚の家を訪れました。
小高い山の上で、天然クーラーと薪ストーブで自然を満喫している御夫妻です。

広々としたフロアにはピアノ、チェンバロ、クラヴィコードが並び、静かな雰囲気の中でのんびりおしゃべりを楽しんだ後、翌朝空路博多から学生時代からの憧れの地、五島列島へ向かいました。
大気が不安定なため飛行機が飛ぶかどうか不安でしたが、一時間遅れで出発。
飛行機からは真っ白な雲しか見えませんでしたが無事福江に到着。
空港からはタクシーに乗り、まずは運転手さんお薦めの地元の方に親しまれているという寿司店で昼食をとることにしました。

博多でもよく見かけた魚で、九州では「クロ」と呼ばれるメジナがここでもよく登場しました。
海に囲まれ、海の幸は豊富なので切り身も分厚いです。
ついお刺身盛り合わせと握りを頼んでしまったらお刺身だけでお腹がいっぱいになる量で、握りはお持ち帰りになりました。
ホテルに荷物を置いた後、タクシーで白亜の優美な「水ノ浦教会」を訪れました。

禁教の高札撤去から7年後の1880年(明治13年)最初の教会が建てられましたが、潮風による老朽化が進み、1938年(昭和13年)、名工と言われた鉄川与助氏により建て替えられました。
内部はこじんまりとしていますが、静かな祈りの場としての簡素な美しさが感じられました。
小高い丘の上にあるのでロケーションも素晴らしいです。

因みに福江空港にはステンドグラス製のこんな「水ノ浦教会像」が展示されています。

この後「遣唐使ふるさと館」へ立ち寄り、展示とシアターを拝見、この日は疲れも出てきていたので早めに休みました。
翌日午前中は「五島めぐり観光バス」で、「堂崎教会」「鐙瀬(あぶんぜ)溶岩海岸」等を廻りました。

ゴシック様式の堂崎教会は1880年仮聖堂が建立、1907年(明治40年)に現在の教会が完成し、1974年には長崎県の文化財に指定されました。
内部には「堂崎天主堂キリシタン資料館」が開設され、布教から迫害をうけた時代等の資料が展示されています。
教会入口は海に向かっていて、信徒達が船で通ったことが窺え、信仰の篤さに胸を打たれます。
教会入口には司教の像と共に、長崎西坂で処刑された26聖人の一人で唯一の五島出身者「ヨハネ五島」の磔刑像もみられます。

どんよりとした空模様で、海の風景はあまり見えませんでしたが、辛うじて「鐙瀬溶岩海岸」が見えました。

五島一族の争い(1507年)でこの地まで逃れてきた16代囲公の鐙がここで切れたことから「鐙瀬(あぶんぜ)」の名が付いたそうです。
晴れていれば荒々しい海岸線が見渡せたことでしょう。
そんな訳で、車窓からの「鬼岳」も見えず、武家屋敷通りを通って福江港へ戻りました。
丁度お昼時だったので、今日もタクシー運転手さんに教えていただいたお店へ行ってみました。
もう30年程になる庶民的うどん屋さんで、「うどんと炊き込みご飯のセット」を薦められました。
ちょっと量が多い様ですが、「炊き込みご飯」は半分でも良いので是非!とのことでした。
行ってみると、ほぼ満席。(カウンター席のみ)私はワカメうどんと炊き込みご飯を注文。ワカメの美味しさにビックリ。
特別に注文されているそうです。ご飯は味がしっかり染み込んでとてもおいしかったです。
お店のご主人も奥様もとても気さくで、お客様も皆さん和気あいあいといった雰囲気でした。
この後、あまり時間が無く、遠くまでは行かれないので、近くの武家屋敷通りへ行くことにしたのですが、お店のお客様がそこまで案内してくださいました。五島に着いてから気づいたのですが、通りすがりの方が皆さん「こんにちは」と声を掛けて下さいます。私が大きなカメラを手にして歩いていたからかもしれませんが、なんともほのぼのとした空気が感じられ、出会った方々も皆さんとても親切だったこともあり、五島の印象は極めて好ましいものとなりました。
できればもう一泊したかったのですが、余裕が無く、この後武家屋敷跡、五島観光歴史資料館を回って福江空港へ向かいました。
小高い山の上で、天然クーラーと薪ストーブで自然を満喫している御夫妻です。

広々としたフロアにはピアノ、チェンバロ、クラヴィコードが並び、静かな雰囲気の中でのんびりおしゃべりを楽しんだ後、翌朝空路博多から学生時代からの憧れの地、五島列島へ向かいました。
大気が不安定なため飛行機が飛ぶかどうか不安でしたが、一時間遅れで出発。
飛行機からは真っ白な雲しか見えませんでしたが無事福江に到着。
空港からはタクシーに乗り、まずは運転手さんお薦めの地元の方に親しまれているという寿司店で昼食をとることにしました。

博多でもよく見かけた魚で、九州では「クロ」と呼ばれるメジナがここでもよく登場しました。
海に囲まれ、海の幸は豊富なので切り身も分厚いです。
ついお刺身盛り合わせと握りを頼んでしまったらお刺身だけでお腹がいっぱいになる量で、握りはお持ち帰りになりました。
ホテルに荷物を置いた後、タクシーで白亜の優美な「水ノ浦教会」を訪れました。

禁教の高札撤去から7年後の1880年(明治13年)最初の教会が建てられましたが、潮風による老朽化が進み、1938年(昭和13年)、名工と言われた鉄川与助氏により建て替えられました。
内部はこじんまりとしていますが、静かな祈りの場としての簡素な美しさが感じられました。
小高い丘の上にあるのでロケーションも素晴らしいです。

因みに福江空港にはステンドグラス製のこんな「水ノ浦教会像」が展示されています。

この後「遣唐使ふるさと館」へ立ち寄り、展示とシアターを拝見、この日は疲れも出てきていたので早めに休みました。
翌日午前中は「五島めぐり観光バス」で、「堂崎教会」「鐙瀬(あぶんぜ)溶岩海岸」等を廻りました。

ゴシック様式の堂崎教会は1880年仮聖堂が建立、1907年(明治40年)に現在の教会が完成し、1974年には長崎県の文化財に指定されました。
内部には「堂崎天主堂キリシタン資料館」が開設され、布教から迫害をうけた時代等の資料が展示されています。
教会入口は海に向かっていて、信徒達が船で通ったことが窺え、信仰の篤さに胸を打たれます。
教会入口には司教の像と共に、長崎西坂で処刑された26聖人の一人で唯一の五島出身者「ヨハネ五島」の磔刑像もみられます。

どんよりとした空模様で、海の風景はあまり見えませんでしたが、辛うじて「鐙瀬溶岩海岸」が見えました。

五島一族の争い(1507年)でこの地まで逃れてきた16代囲公の鐙がここで切れたことから「鐙瀬(あぶんぜ)」の名が付いたそうです。
晴れていれば荒々しい海岸線が見渡せたことでしょう。
そんな訳で、車窓からの「鬼岳」も見えず、武家屋敷通りを通って福江港へ戻りました。
丁度お昼時だったので、今日もタクシー運転手さんに教えていただいたお店へ行ってみました。
もう30年程になる庶民的うどん屋さんで、「うどんと炊き込みご飯のセット」を薦められました。
ちょっと量が多い様ですが、「炊き込みご飯」は半分でも良いので是非!とのことでした。
行ってみると、ほぼ満席。(カウンター席のみ)私はワカメうどんと炊き込みご飯を注文。ワカメの美味しさにビックリ。
特別に注文されているそうです。ご飯は味がしっかり染み込んでとてもおいしかったです。
お店のご主人も奥様もとても気さくで、お客様も皆さん和気あいあいといった雰囲気でした。
この後、あまり時間が無く、遠くまでは行かれないので、近くの武家屋敷通りへ行くことにしたのですが、お店のお客様がそこまで案内してくださいました。五島に着いてから気づいたのですが、通りすがりの方が皆さん「こんにちは」と声を掛けて下さいます。私が大きなカメラを手にして歩いていたからかもしれませんが、なんともほのぼのとした空気が感じられ、出会った方々も皆さんとても親切だったこともあり、五島の印象は極めて好ましいものとなりました。
できればもう一泊したかったのですが、余裕が無く、この後武家屋敷跡、五島観光歴史資料館を回って福江空港へ向かいました。
2014年07月30日
クルージングで浦安花火見物
先日知人に誘われ、東京湾クルージングに出掛けました。
乗客6名、クルー3名の計9名です。
クルージングは初めてなので興味津々。偶々この日は隅田川の花火大会、浦安花火大会等、あちこちの花火大会があり、大賑わいでした。
出発時は海も静かで、ワイワイ賑やか出航、お隣を走るボートにも声援を送る程でしたが、

次第に海が荒れはじめ、

かなりの揺れに耐えながらのクルーズとなり、2名程が船酔いでダウンしてしまいました。

それでも何とか写真を撮るべく頑張り、滅多に撮れないゲートブリッジ下の通過時の映像にも成功。
但し、羽田空港への旅客機の着陸は、あまりの速さと船の揺れとで、写真撮影は断念しました。
途中、形だけですが、操縦も体験させていただきました。

船は4時に出航したので、海は次第に黄昏て・・・

遠目には穏やかにみえますが、かなり揺れていました。
ここで取り敢えず小さな港へ避難してシャンパンで乾杯!となりました。

船上ではガラスは使えないので、特殊なグラスだそうです。
そういえば、キャビンでガラガラと音がして、食器類が転がっていました。

この船は知人の会社がオーナーになっているそうなので、アパレル関連の会社名(ビノン株式会社)の名の入った帆が晴れやかにはためいています。

再び出航して浦安花火大会の会場へと向かいました。
船は時に大きくアップダウン、水しぶきも半端ではありません。全身びしょ濡れの人も・・・。
こちらは海上保安庁のレーダーがある場所です。

浦安沖へ着く頃には陽も傾き、

場所を確保したのですが、風が激しく、碇を下ろしても船がクルクル回ってしまい、浦安寄りに入るとすぐに巡視艇が近寄ってきて、移動を命じられる・・・という過酷な状況でした。
この頃には皆さん疲れが出て、仮眠。
漸く花火が始まりましたが、写真は思うように撮れませんでした。

それでも、海から見る花火は格別で、堪能しました。
この日はあちこちで花火大会があったようで、ディズニーランドの花火の他にも2つ程、花火の上がるのが見えました。
観覧車の鮮やか光を横に見ながら、

東京湾クルージングを終了。
帰途も大変な人混みでした。
乗客6名、クルー3名の計9名です。
クルージングは初めてなので興味津々。偶々この日は隅田川の花火大会、浦安花火大会等、あちこちの花火大会があり、大賑わいでした。
出発時は海も静かで、ワイワイ賑やか出航、お隣を走るボートにも声援を送る程でしたが、

次第に海が荒れはじめ、

かなりの揺れに耐えながらのクルーズとなり、2名程が船酔いでダウンしてしまいました。

それでも何とか写真を撮るべく頑張り、滅多に撮れないゲートブリッジ下の通過時の映像にも成功。
但し、羽田空港への旅客機の着陸は、あまりの速さと船の揺れとで、写真撮影は断念しました。
途中、形だけですが、操縦も体験させていただきました。

船は4時に出航したので、海は次第に黄昏て・・・

遠目には穏やかにみえますが、かなり揺れていました。
ここで取り敢えず小さな港へ避難してシャンパンで乾杯!となりました。

船上ではガラスは使えないので、特殊なグラスだそうです。
そういえば、キャビンでガラガラと音がして、食器類が転がっていました。

この船は知人の会社がオーナーになっているそうなので、アパレル関連の会社名(ビノン株式会社)の名の入った帆が晴れやかにはためいています。

再び出航して浦安花火大会の会場へと向かいました。
船は時に大きくアップダウン、水しぶきも半端ではありません。全身びしょ濡れの人も・・・。
こちらは海上保安庁のレーダーがある場所です。

浦安沖へ着く頃には陽も傾き、

場所を確保したのですが、風が激しく、碇を下ろしても船がクルクル回ってしまい、浦安寄りに入るとすぐに巡視艇が近寄ってきて、移動を命じられる・・・という過酷な状況でした。
この頃には皆さん疲れが出て、仮眠。
漸く花火が始まりましたが、写真は思うように撮れませんでした。

それでも、海から見る花火は格別で、堪能しました。
この日はあちこちで花火大会があったようで、ディズニーランドの花火の他にも2つ程、花火の上がるのが見えました。
観覧車の鮮やか光を横に見ながら、

東京湾クルージングを終了。
帰途も大変な人混みでした。
2014年07月25日
宮地嶽(みやじだけ)神社
全国にある宮地嶽神社の総本社で、創建は社伝によると1600年前とされ、息長足比売命(おきながたらしひめのみこと)別名「神功(じんぐう)皇后」(応神天皇の母君)が御祭神とされます。

拝殿正面には巨大注連縄がかけられていますが、、長さ135m、重さ35tと日本一だそうです。

この神社には他にも日本一の大きさといわれる大太鼓、重さ450kgの青銅製大鈴があり、「三つの日本一」といわれているそうです。
この神社には「奥の宮八社」と呼ばれる社が祀られ、その中の不動神社(史跡)には約260年以上前に出土した、全国でも第一級の大きさの横穴式石室を有する巨大古墳あり、約6世紀末の建立と見られています。その石室は、全長23m、高さ幅共5mを超える巨大な石を積み重ねて造られており、大太刀、馬具類、瑠璃壷、ガラス板等300点程が発見され、その内20点が国宝に指定されています。

特に黄金を使った品々は素晴らしく、金銅製の冠には黄金に龍や虎の透かし彫りが施されているそうです。
教科書にも載っている金銅製の鐙等、華やか王朝の姿が想像されます。
この様に、古来より宮地獄神社は崇高かつ裕福な神として恭われ、現在では開運、商売繁盛の神として崇められるようになりました。
嘗ては古墳がそのままで、石室を通り中まで拝観できたそうですが、20 数年前に建物で覆われたそうです。
全部の神社は廻りきれませんでしたが、鮮やか鳥居が沢山並ぶ「稲荷神社」は目に付きやすいです。

境内にはこんな立派な石碑もありました。

ここ宮司村(みやじむら)は痩せた農地で、常に水不足に悩まされていましたが、村民総出で溜池造りをして水不足を解消、年貢米はいつも一番に納め、天明の大飢饉(天明5年・1785年)時にもこの村だけが年貢米の返上を願い出ず完納したため、時の藩主から他村の模範として表彰されまました。寛政2年(1790年)褒美として米六百俵が贈られ、村民はこれを代々伝えるべく、この褒美の一部で、村内出生児に産着を贈ることとし、現在でもこの習わしが続けられているそうです。
歴史の感じられる静かな神社でした。

拝殿正面には巨大注連縄がかけられていますが、、長さ135m、重さ35tと日本一だそうです。

この神社には他にも日本一の大きさといわれる大太鼓、重さ450kgの青銅製大鈴があり、「三つの日本一」といわれているそうです。
この神社には「奥の宮八社」と呼ばれる社が祀られ、その中の不動神社(史跡)には約260年以上前に出土した、全国でも第一級の大きさの横穴式石室を有する巨大古墳あり、約6世紀末の建立と見られています。その石室は、全長23m、高さ幅共5mを超える巨大な石を積み重ねて造られており、大太刀、馬具類、瑠璃壷、ガラス板等300点程が発見され、その内20点が国宝に指定されています。

特に黄金を使った品々は素晴らしく、金銅製の冠には黄金に龍や虎の透かし彫りが施されているそうです。
教科書にも載っている金銅製の鐙等、華やか王朝の姿が想像されます。
この様に、古来より宮地獄神社は崇高かつ裕福な神として恭われ、現在では開運、商売繁盛の神として崇められるようになりました。
嘗ては古墳がそのままで、石室を通り中まで拝観できたそうですが、20 数年前に建物で覆われたそうです。
全部の神社は廻りきれませんでしたが、鮮やか鳥居が沢山並ぶ「稲荷神社」は目に付きやすいです。

境内にはこんな立派な石碑もありました。

ここ宮司村(みやじむら)は痩せた農地で、常に水不足に悩まされていましたが、村民総出で溜池造りをして水不足を解消、年貢米はいつも一番に納め、天明の大飢饉(天明5年・1785年)時にもこの村だけが年貢米の返上を願い出ず完納したため、時の藩主から他村の模範として表彰されまました。寛政2年(1790年)褒美として米六百俵が贈られ、村民はこれを代々伝えるべく、この褒美の一部で、村内出生児に産着を贈ることとし、現在でもこの習わしが続けられているそうです。
歴史の感じられる静かな神社でした。
2014年07月23日
金台(こんたい)寺と宗像大社
お墓は博多から北へ向かった遠賀群にあり「時宗遊行派」(一遍開祖)とのことで、御住職は先日鎌倉の遊行寺の研修会に出掛けられたそうです。
無事お墓参りを済ませた頃急に雨が降り出し、境内の地蔵堂で雨宿りさせていただくことになりました。
堂内には2.45mの木彫り、彩色された江戸時代中期作の子安地蔵が安置され、

その胎内には源頼朝が出陣の折兜に仕込んで念持仏としていたという金銅の小地蔵がおさめられていたそうですが、現在は別に祀られているとのことで、年に一度だけ公開されるそうです。そんなお話を伺い、鎌倉銘菓の鳩サブレを頂いている内に、奥様がその「小地蔵像」を持ってきて下さり、思い掛けず拝見することが出来ました。

小柄ながら穏やか表情の優しげなお顔で、間近に見られる機会を得られたことに感謝です。
雨は土砂降りになり、仕方ないので先に昼食を摂ることにしました。
この日も海の幸を満喫しました。

アワビのステーキと、

おまかせ寿司のコースでしたが、どちらもとても美味しくいただきました。
特にイカは今が旬なので、甘くて感激しました。
食事を終えて外へ出るとすっかり雨が上がっていたので、予定通り先ずは宗像大社へ向かいました。

でも、残念ながら現在大掛かりな改修工事中で、建物は殆ど見えません。仕方なく「神宝館」を拝観しましたが、国宝、重文も多く、見ごたえあります。
「宗像大社」は、沖ノ島の沖津宮、筑前大島の中津宮、宗像市田島の辺津宮の三社の総称ですが、現在では辺津宮のみを指す場合も多い様です。
古くから海上・交通安全の神として信仰されていましたが、現在では陸上・交通安全の神としても信仰を集め、福岡市内では宗像大社のステッカーを貼った車が多数見られるそうです。
次に「宮地獄(みやじだけ)神社」へ向かいました。
無事お墓参りを済ませた頃急に雨が降り出し、境内の地蔵堂で雨宿りさせていただくことになりました。
堂内には2.45mの木彫り、彩色された江戸時代中期作の子安地蔵が安置され、

その胎内には源頼朝が出陣の折兜に仕込んで念持仏としていたという金銅の小地蔵がおさめられていたそうですが、現在は別に祀られているとのことで、年に一度だけ公開されるそうです。そんなお話を伺い、鎌倉銘菓の鳩サブレを頂いている内に、奥様がその「小地蔵像」を持ってきて下さり、思い掛けず拝見することが出来ました。

小柄ながら穏やか表情の優しげなお顔で、間近に見られる機会を得られたことに感謝です。
雨は土砂降りになり、仕方ないので先に昼食を摂ることにしました。
この日も海の幸を満喫しました。

アワビのステーキと、

おまかせ寿司のコースでしたが、どちらもとても美味しくいただきました。
特にイカは今が旬なので、甘くて感激しました。
食事を終えて外へ出るとすっかり雨が上がっていたので、予定通り先ずは宗像大社へ向かいました。

でも、残念ながら現在大掛かりな改修工事中で、建物は殆ど見えません。仕方なく「神宝館」を拝観しましたが、国宝、重文も多く、見ごたえあります。
「宗像大社」は、沖ノ島の沖津宮、筑前大島の中津宮、宗像市田島の辺津宮の三社の総称ですが、現在では辺津宮のみを指す場合も多い様です。
古くから海上・交通安全の神として信仰されていましたが、現在では陸上・交通安全の神としても信仰を集め、福岡市内では宗像大社のステッカーを貼った車が多数見られるそうです。
次に「宮地獄(みやじだけ)神社」へ向かいました。
2014年07月21日
博多祇園山笠
旧知の方のお墓参りを10年越しで果たすべく、九州の旅を企画しました。
お墓は博多にあるので、先ずは博多に到着したのですが、人で溢れていて、何事か?と思ったら、「博多山笠」の「追い山」を明日に控えているとのこと・・・。取り敢えず荷物を置いて知人に連絡、この日は博多から脱出することにしました。
知人の車で海辺を走り、糸島方面へ向かい、博多湾沿いの「空」というお店でゆっくりとお食事することになりました。

目の前には海が広がり、

美味しい海の幸を戴きながらのんびりおしゃべりを楽しみ、帰路は夜景も楽しんで、

ホテル着。偶然にせよ、折角のチャンスなので、翌早朝の「追い山」見物に出掛ける事にしました。
朝4時59分出発とのことで、待っていると、人の群れが流れ始めたので、取り敢えず後を付いてゆくことにしました。
博多山笠は、7月1日の祭り初日、山笠の流区地域を清める行事に始まり、
10日の流れがき、11日の朝山笠、他流がき、14日の流れがき、そして最終日15日の追い山笠となり、大太鼓の合図と共に一番笠から順に「櫛田入り」。その後境内を出て、約5キロの「追い山笠コース」を須崎町の廻り止め(ゴール)を目指して懸命に山笠をひき、所要時間を計測します。
何も解らなかったので、人の流れの後を追うと、櫛田神社近くへ向かい、神社から走り出す山笠を迎える位置へ出ました。人混みが激しく、交通規制もされていてとても移動は無理なので、ここで待つことになりましたが、何せ勢いよく飛び出してくるので、写真を撮るのが至難でした。(因みに、33秒〜38秒位です)

山笠の担ぎ手は皆さん法被に締め込み(褌)姿で、勇ましいのですが、子供達の締め込み姿の可愛いこと!写真に撮りたかったのですが、人垣がすごく、とても前へは出られませんでした。
七つの流のかき山と上川端通の飾り山が、一台づつ紹介されながら出発しました。

博多市内には1日〜15日まで14箇所に飾り山笠が公開されますが、

これは博多駅前の「黒田官兵衛」に因んだ山笠です。
博多駅前にはこんなプレートも掛けられていて、

歴代優勝者の足形が刻まれ、懐かしい名前も見つけました。
思い掛け無く「博多祇園山笠」を見物できましたが、このお祭りは国の重要無形文化財に指定されているそうで、7月28日にはBSプレミアムで放送されるそうです。
この後、遠賀群芦屋の「金台寺(こんだいじ)」へお墓参りに向かいました。
お墓は博多にあるので、先ずは博多に到着したのですが、人で溢れていて、何事か?と思ったら、「博多山笠」の「追い山」を明日に控えているとのこと・・・。取り敢えず荷物を置いて知人に連絡、この日は博多から脱出することにしました。
知人の車で海辺を走り、糸島方面へ向かい、博多湾沿いの「空」というお店でゆっくりとお食事することになりました。

目の前には海が広がり、

美味しい海の幸を戴きながらのんびりおしゃべりを楽しみ、帰路は夜景も楽しんで、

ホテル着。偶然にせよ、折角のチャンスなので、翌早朝の「追い山」見物に出掛ける事にしました。
朝4時59分出発とのことで、待っていると、人の群れが流れ始めたので、取り敢えず後を付いてゆくことにしました。
博多山笠は、7月1日の祭り初日、山笠の流区地域を清める行事に始まり、
10日の流れがき、11日の朝山笠、他流がき、14日の流れがき、そして最終日15日の追い山笠となり、大太鼓の合図と共に一番笠から順に「櫛田入り」。その後境内を出て、約5キロの「追い山笠コース」を須崎町の廻り止め(ゴール)を目指して懸命に山笠をひき、所要時間を計測します。
何も解らなかったので、人の流れの後を追うと、櫛田神社近くへ向かい、神社から走り出す山笠を迎える位置へ出ました。人混みが激しく、交通規制もされていてとても移動は無理なので、ここで待つことになりましたが、何せ勢いよく飛び出してくるので、写真を撮るのが至難でした。(因みに、33秒〜38秒位です)

山笠の担ぎ手は皆さん法被に締め込み(褌)姿で、勇ましいのですが、子供達の締め込み姿の可愛いこと!写真に撮りたかったのですが、人垣がすごく、とても前へは出られませんでした。
七つの流のかき山と上川端通の飾り山が、一台づつ紹介されながら出発しました。

博多市内には1日〜15日まで14箇所に飾り山笠が公開されますが、

これは博多駅前の「黒田官兵衛」に因んだ山笠です。
博多駅前にはこんなプレートも掛けられていて、

歴代優勝者の足形が刻まれ、懐かしい名前も見つけました。
思い掛け無く「博多祇園山笠」を見物できましたが、このお祭りは国の重要無形文化財に指定されているそうで、7月28日にはBSプレミアムで放送されるそうです。
この後、遠賀群芦屋の「金台寺(こんだいじ)」へお墓参りに向かいました。
2014年07月13日
ブログお休みのお知らせ

今年は大雪のせいで、我が家のバラの咲き具合があまり元気でなかったため、バラのご紹介は控えましたが、7月に入って、少し小さめですが元気を回復しつつあります。

秋には沢山咲いてくれることを期待しています。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。
一週間程、ブログお休みしますが、復活後又お会いできるのを楽しみにしています。
2014年07月10日
キュウリの肉詰め
相変わらずキュウリに追われている毎日ですが、今度は巨大キュウリレシピを考えてみました。

巨大キュウリの長さを三等分位に切り、種を取って皮をむき、(先に皮をむくと種が取りにくくなります)軽く塩をしておきます。
今回は鶏挽肉を使いましたが、好みで豚挽肉でも良いと思います。
生姜のみじん切り、胡椒、昆布茶、XO醤、ナンプラー少々で味を整え、水気を取ったキュウリに詰め込み、全体に粉をまぶし(私はコーンスターチを使用)、油をひいたフライパンで、先ずは肉の面をしっかい焼いて肉が飛び出さないようにしてから、全体にこんがり焼き色をつけ、リーペリンソースを少々落として香りを付けて出来上がりです。
皮を取り除いたので、きゅうり臭さがなくなり、さっぱりとしてとても食べやすくなりました。
調味料は全部入れる必要は無く、手近なものを利用してください。但し、今回はリーペリンソースが決め手なので、手近なウスターソース等で試してみてください。
巨大なキュウリの調理法としておすすめです。

巨大キュウリの長さを三等分位に切り、種を取って皮をむき、(先に皮をむくと種が取りにくくなります)軽く塩をしておきます。
今回は鶏挽肉を使いましたが、好みで豚挽肉でも良いと思います。
生姜のみじん切り、胡椒、昆布茶、XO醤、ナンプラー少々で味を整え、水気を取ったキュウリに詰め込み、全体に粉をまぶし(私はコーンスターチを使用)、油をひいたフライパンで、先ずは肉の面をしっかい焼いて肉が飛び出さないようにしてから、全体にこんがり焼き色をつけ、リーペリンソースを少々落として香りを付けて出来上がりです。
皮を取り除いたので、きゅうり臭さがなくなり、さっぱりとしてとても食べやすくなりました。
調味料は全部入れる必要は無く、手近なものを利用してください。但し、今回はリーペリンソースが決め手なので、手近なウスターソース等で試してみてください。
巨大なキュウリの調理法としておすすめです。
タグ :キュウリのレシピ
2014年07月07日
干しキュウリレシピ
水餃子が成功したので、他のレシピも考えてみました。
先ずは煎り豆腐とキュウリの胡麻和えです。

煎り豆腐は、酒、ジャコ、生姜の千切り、干しキュウリ、おぼろ昆布の粉(昆布茶でも代用可)、を加熱し大葉の千切りをあしらいましたが、生姜が効いて美味しくしあがりました。
キュウリの胡麻和えは、油で炒めてから酒、味醂、醤油で味付けしてごまと和えましたがキュウリ臭さがかなり残ってしまいました。ごまを多めにするか、ごま油で炒める等の改良が必要で、皮も口に少し残る様でした。
次は揚げワンタンと素揚げキュウリです。

ワンタンの具は先日の水餃子と同じです。
キュウリ臭さも無く美味しくいただけましたが、こちらも酢を効かせたほうが美味しい様です。
素揚げは、カリっとは揚がりませんが、食べやすくはなりました。これは他の料理に加えてみても良いようです。
胡麻和えにも酢を加えると良いのかもしれません。
それにしても又々キュウリが収穫でき、キュウリに埋もれそうです。
先ずは煎り豆腐とキュウリの胡麻和えです。

煎り豆腐は、酒、ジャコ、生姜の千切り、干しキュウリ、おぼろ昆布の粉(昆布茶でも代用可)、を加熱し大葉の千切りをあしらいましたが、生姜が効いて美味しくしあがりました。
キュウリの胡麻和えは、油で炒めてから酒、味醂、醤油で味付けしてごまと和えましたがキュウリ臭さがかなり残ってしまいました。ごまを多めにするか、ごま油で炒める等の改良が必要で、皮も口に少し残る様でした。
次は揚げワンタンと素揚げキュウリです。

ワンタンの具は先日の水餃子と同じです。
キュウリ臭さも無く美味しくいただけましたが、こちらも酢を効かせたほうが美味しい様です。
素揚げは、カリっとは揚がりませんが、食べやすくはなりました。これは他の料理に加えてみても良いようです。
胡麻和えにも酢を加えると良いのかもしれません。
それにしても又々キュウリが収穫でき、キュウリに埋もれそうです。
2014年07月03日
キュウリ餃子
今年は雨が多いせいかキュウリの成長が例年より活発で、2,3日であっという間に巨大になる上、一度に10本も収穫できてしまいます。とても食べきれないので、遂に生で食べることを諦め、干しキュウリにして加熱して食べることにしました。

太いものは種を取って薄切りし、晴れた日に一日干したところ、絞っても水分が出ない所まで乾燥できました。
丁度餃子を作るつもりだったので、利用してみることにしました。
材料は、豚挽肉、干しきゅうりの刻んだもの、生姜の千切り、ニンニク少々のみじん切り、塩、胡椒、です。
今回は水餃子の皮を用意してあったので、こちらにしました。

不思議とキュウリの青臭みが消え、シャキシャキ感が残り、爽やか味わいになりました。
タレは、酢、醤油、ラー油で、酢を効かせるとより美味しく感じました。
この時期お薦めです。
これに味をしめ、今日はカレーそばにも入れてみましたが、やはりシャキシャキ感が何とも言えません。
すっかりハマってしまい、色々挑戦してみようと思っています。
但し、干しキュウリは、これから気温が上がると乾燥するまでに傷んでしまうと思いますので、気温が30度近くになると無理かと思います。今のうちがお薦めです。

太いものは種を取って薄切りし、晴れた日に一日干したところ、絞っても水分が出ない所まで乾燥できました。
丁度餃子を作るつもりだったので、利用してみることにしました。
材料は、豚挽肉、干しきゅうりの刻んだもの、生姜の千切り、ニンニク少々のみじん切り、塩、胡椒、です。
今回は水餃子の皮を用意してあったので、こちらにしました。

不思議とキュウリの青臭みが消え、シャキシャキ感が残り、爽やか味わいになりました。
タレは、酢、醤油、ラー油で、酢を効かせるとより美味しく感じました。
この時期お薦めです。
これに味をしめ、今日はカレーそばにも入れてみましたが、やはりシャキシャキ感が何とも言えません。
すっかりハマってしまい、色々挑戦してみようと思っています。
但し、干しキュウリは、これから気温が上がると乾燥するまでに傷んでしまうと思いますので、気温が30度近くになると無理かと思います。今のうちがお薦めです。
2014年07月01日
ジャック・カロ展
前回ブログに載せた銀座「北欧の匠ビル」を出るとすぐに、こんなお店を見つけ、思わず写真を撮ってしまいました。

「箒専門店」です!今でも現役なんて感動的です。
時間も無く、店内は見られませんでしたが、どんな箒が並んでいるのでしょうか?何時か覗いてみたいものです。
この後友人と、国立西洋美術館での「ジャック・カロ展」を鑑賞しました。
実は展示期日は既に過ぎてしまったのですが、興味深かったので紹介させて頂きます。

17世紀初頭のロレーヌ地方(現在はフランスの一部)で活躍した銅版画家で、40数年の生涯に1400点の作品を残していて、西洋美術館には400点所蔵され、今回その内の220点が展示されました。
彼の作品のテーマは、多彩で、華やか宮廷生活、兵士、道化、酔っ払い、乞食、小人(障害者)、等様々ですが、特に知られているのは「戦争の惨禍」と題されたシリーズ作品で、その中では、略奪、放火する兵士や、彼らを処刑する上官、私刑にする農民の姿がリアル過ぎるまでに描かれています。又、表現が極めて緻密で、驚嘆に値しますが、これは、彼の試行錯誤を繰り返した末のエッチング技法の技術革新による所が大きい様です。例えば、先端が傾斜した楕円形のエッチング針を多用して膨らみのある線を可能にしたり、エッチングに用いる防蝕剤をそれまでのロウではなくリュート製作者の使う硬いニスにすることで、彫られた線がより深く腐蝕されるようになり、印刷に使う版の寿命を延ばすと同時に酸の過剰な侵食による失敗を劇的に減らす事にも成功しています。
この様な技術革新による成果は、エッチングによる高度に細密な表現を可能にしています。
その為、会場内にはルーペが置かれ、自由に使える様になっていましたが、皆さん、つい作品に近づき過ぎて、「作品には近づき過ぎないで下さい」とあちこちで注意されていました。
ルーペで作品鑑賞したのは初めてでした。
会場内には更に、DNP大日本印刷のデジタル展示技術により開発された「みどころルーペ」が導入され、タッチパネルディスプレイを用いて、肉眼では気付きにくい作品の細部を拡大して鑑賞できるシステムが2箇所設置されていましたが、一人が占領してしまうと中々空かないので、操作することはできませんでした。
異次元の様な細密な世界を垣間見られて感激しました。
今回は、この展示の他、「平野啓一郎が選ぶ西洋美術の名品展」も鑑賞できました。

西洋美術館の常設展示には素晴らしい作品が目白押しなので、こうして広く紹介されるのは大変良い企画だと思いました。
友人も、素晴らしい作品が並んでいることに驚いていました。
常設展は是非またゆっくり鑑賞したいものです。

「箒専門店」です!今でも現役なんて感動的です。
時間も無く、店内は見られませんでしたが、どんな箒が並んでいるのでしょうか?何時か覗いてみたいものです。
この後友人と、国立西洋美術館での「ジャック・カロ展」を鑑賞しました。
実は展示期日は既に過ぎてしまったのですが、興味深かったので紹介させて頂きます。

17世紀初頭のロレーヌ地方(現在はフランスの一部)で活躍した銅版画家で、40数年の生涯に1400点の作品を残していて、西洋美術館には400点所蔵され、今回その内の220点が展示されました。
彼の作品のテーマは、多彩で、華やか宮廷生活、兵士、道化、酔っ払い、乞食、小人(障害者)、等様々ですが、特に知られているのは「戦争の惨禍」と題されたシリーズ作品で、その中では、略奪、放火する兵士や、彼らを処刑する上官、私刑にする農民の姿がリアル過ぎるまでに描かれています。又、表現が極めて緻密で、驚嘆に値しますが、これは、彼の試行錯誤を繰り返した末のエッチング技法の技術革新による所が大きい様です。例えば、先端が傾斜した楕円形のエッチング針を多用して膨らみのある線を可能にしたり、エッチングに用いる防蝕剤をそれまでのロウではなくリュート製作者の使う硬いニスにすることで、彫られた線がより深く腐蝕されるようになり、印刷に使う版の寿命を延ばすと同時に酸の過剰な侵食による失敗を劇的に減らす事にも成功しています。
この様な技術革新による成果は、エッチングによる高度に細密な表現を可能にしています。
その為、会場内にはルーペが置かれ、自由に使える様になっていましたが、皆さん、つい作品に近づき過ぎて、「作品には近づき過ぎないで下さい」とあちこちで注意されていました。
ルーペで作品鑑賞したのは初めてでした。
会場内には更に、DNP大日本印刷のデジタル展示技術により開発された「みどころルーペ」が導入され、タッチパネルディスプレイを用いて、肉眼では気付きにくい作品の細部を拡大して鑑賞できるシステムが2箇所設置されていましたが、一人が占領してしまうと中々空かないので、操作することはできませんでした。
異次元の様な細密な世界を垣間見られて感激しました。
今回は、この展示の他、「平野啓一郎が選ぶ西洋美術の名品展」も鑑賞できました。

西洋美術館の常設展示には素晴らしい作品が目白押しなので、こうして広く紹介されるのは大変良い企画だと思いました。
友人も、素晴らしい作品が並んでいることに驚いていました。
常設展は是非またゆっくり鑑賞したいものです。
2014年06月29日
銀座「北欧の匠」ビルのギャラリー
先日、友人と上野の西洋美術館で待ち合わせたのですが、時間があったので、銀座の<北欧の匠ビル>三階のギャラリー[祥]での「北欧の作家たち展」をのぞいてみました。
場所は銀座といっても地下鉄京橋駅近くで、ビル1、2Fには北欧雑貨が所狭しと並べられていました。
こじんまりとしたギャラリーで、作品数は少なかったのですが、不思議な雰囲気に包まれ、楽しい時間が過ごせました。

これは、M・セーゲルトゥレムの銅版画ですが、殆どの作家が日本では知られていないそうです。
他にも、
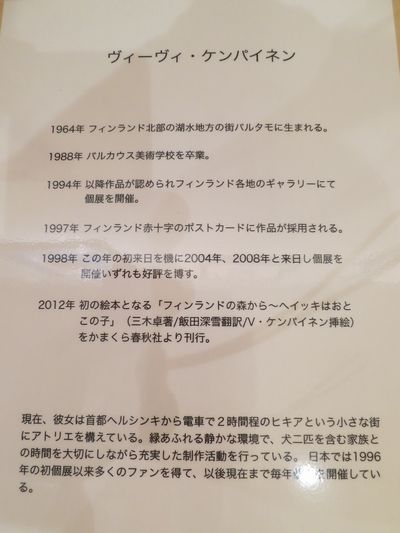
の様な作家7人の作品が並べられ、なぜか親しみのある空気が感じられました。
たまたま私一人だったので、主催されている方とゆっくりおしゃべりが出来ました。
このギャラリーでは毎年北欧の作家の展示をされていて、今回は5回目だそうですが、日本でも少しづつ評価されてきている・・・とのことでした。面白いことに、このギャラリーは北欧関連の展示にのみ貸し出されるそうです。
今回、北欧の作家の作品だけを見ていて、何か日本人に近い自然観が見えてくるように思いました。特に、森に関しては、何かが宿り、森の空気に包まれ生かされている・・・といった畏敬の心に触れ、何故か親密さを感じてしまいます。
色彩はかなりカラフルなのですが、表現が穏やかで、ほのぼのとした雰囲気が漂いますが、今にも森の中からトロールが現れてきそうな、ハラハラ・ドキドキとした緊張感もあり、引き込まれてしまいます。
私はフィンランドが好きなので、色々お話を伺い、北欧の中でもフィンランドは他の国々とは民族も言語も全く異なる異質の国であることを知りました。是非一度訪れてみたいと思います。
作品鑑賞後、1,2Fの雑貨売り場を覗かせて頂きました。
御夫妻と息子さん三人で15年ほど前から開いていらっしゃるそうです。
何とも長閑で、都会とは思えませんでしたが、置かれている物は素晴らしいものばかりでした。


他にも


ユニークな商品が沢山並んでいますが、値段の付いていないものも多く、貴重な品々の様で恐ろしくて手を触れにくかったです。
中にこんなバッグがあり、驚きました。

何方も学生時代に私が使っていたものと全く同じデザインなのです。
とても気に入っていて、長い間大切に使いました。
私の物は国産の安物ですが、このデザインが北欧から来ていたことを今になって知り、北欧との縁を感じます。
残念ながら、この展示会は6月22日で終了してしまいましたが、このビルへは友人と一緒に是非又訪れたいと思っています。
場所は 中央区銀座1-15-13 Tel 03-5524-5657 です。
場所は銀座といっても地下鉄京橋駅近くで、ビル1、2Fには北欧雑貨が所狭しと並べられていました。
こじんまりとしたギャラリーで、作品数は少なかったのですが、不思議な雰囲気に包まれ、楽しい時間が過ごせました。

これは、M・セーゲルトゥレムの銅版画ですが、殆どの作家が日本では知られていないそうです。
他にも、
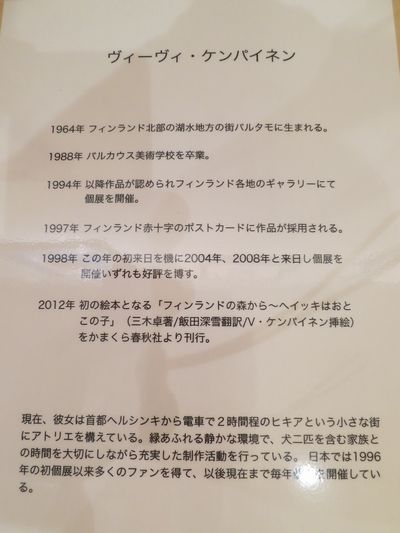
の様な作家7人の作品が並べられ、なぜか親しみのある空気が感じられました。
たまたま私一人だったので、主催されている方とゆっくりおしゃべりが出来ました。
このギャラリーでは毎年北欧の作家の展示をされていて、今回は5回目だそうですが、日本でも少しづつ評価されてきている・・・とのことでした。面白いことに、このギャラリーは北欧関連の展示にのみ貸し出されるそうです。
今回、北欧の作家の作品だけを見ていて、何か日本人に近い自然観が見えてくるように思いました。特に、森に関しては、何かが宿り、森の空気に包まれ生かされている・・・といった畏敬の心に触れ、何故か親密さを感じてしまいます。
色彩はかなりカラフルなのですが、表現が穏やかで、ほのぼのとした雰囲気が漂いますが、今にも森の中からトロールが現れてきそうな、ハラハラ・ドキドキとした緊張感もあり、引き込まれてしまいます。
私はフィンランドが好きなので、色々お話を伺い、北欧の中でもフィンランドは他の国々とは民族も言語も全く異なる異質の国であることを知りました。是非一度訪れてみたいと思います。
作品鑑賞後、1,2Fの雑貨売り場を覗かせて頂きました。
御夫妻と息子さん三人で15年ほど前から開いていらっしゃるそうです。
何とも長閑で、都会とは思えませんでしたが、置かれている物は素晴らしいものばかりでした。


他にも


ユニークな商品が沢山並んでいますが、値段の付いていないものも多く、貴重な品々の様で恐ろしくて手を触れにくかったです。
中にこんなバッグがあり、驚きました。

何方も学生時代に私が使っていたものと全く同じデザインなのです。
とても気に入っていて、長い間大切に使いました。
私の物は国産の安物ですが、このデザインが北欧から来ていたことを今になって知り、北欧との縁を感じます。
残念ながら、この展示会は6月22日で終了してしまいましたが、このビルへは友人と一緒に是非又訪れたいと思っています。
場所は 中央区銀座1-15-13 Tel 03-5524-5657 です。






